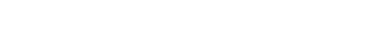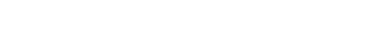令和8年から始まる不動産所有者の氏名・住所の変更登記の義務化について
2025/10/17
令和8年4月1日から、不動産の所有者の氏名・住所の変更登記が義務化されます。この新たな制度は、不動産登記の正確性と透明性を高め、所有者情報の最新化を目的としています。司法書士においても、この義務化に伴う実務対応が求められることから、登記申請を依頼される方への適切な説明・案内が重要となります。本ブログでは、令和8年から始まる不動産所有者の氏名・住所の変更登記の義務化の説明と、これに先立ちすでに始まっている「検索用情報の申出」について分かりやすく解説します。
目次
令和8年4月開始!不動産所有者の氏名・住所の変更登記義務化の背景と目的とは?
令和8年4月1日から、不動産の所有者氏名や住所の変更登記が義務化されることになります。これは、不動産登記の正確性と透明性を高めるための重要な制度変更です。従来は不動産所有者の氏名や住所に変更が生じた場合でもその登記が任意であったことから、所有者情報が古いままですぐさま探索できないなどの問題が生じていました。今回の義務化により、所有者の氏名や住所に変更が生じた際は、変更が生じた日から2年以内に変更の登記をしなければならないことになります。
また、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始されます。「スマート変更登記」をするためには、登記官が所有者の住基ネット情報を検索することになりますが、その前提として、所有者には、その氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。そこで、「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の「検索用情報」を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になりました。
登記申請と同時に検索用情報の申出をする必要がある登記申請の種類等
次に掲げる登記の申請をする場合には、登記官に対し、所有権の登記名義人となる申請人(国内に住所を有する自然人である場合に限る)の検索用情報を申請情報の内容として申し出る必要があります(不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号)による改正後の不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「新規則」といいます。)第158条の39第1項)。
(1) 所有権の保存の登記
(2) 所有権の移転の登記
(3) 合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る)
(4) 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る)
なお、所有権の登記名義人となる者が次のいずれかに該当する場合には、その者の検索用情報を申し出ることはできません。
・法人である場合
・海外居住者である場合
・登記の申請人でない場合(代位者等が登記申請をする場合が該当します。なお、この場合に所有権の登記名義人となる者が国内に住所を有する自然人である場合には、代位登記の完了後、その者から、別途、申出をすることができます。)
検索用情報の具体的な内容
申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです(新規則第158条の39第1項第1号から第5号まで)。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの(※1))
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス(※2)
※1 申請情報の内容とされた氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下「ローマ字氏名」といいます。)については、登記記録に記録(氏名に併記)されることとなります。なお、所有権の登記名義人となる者が通称名を氏名として登記申請をする場合や、登記名義人となる者の外国人住民票にローマ字氏名の記載がない場合には、ローマ字氏名を申請情報の内容とすることを要しません。このような場合には、氏名の振り仮名を申請情報の内容とします。
※2 申請情報の内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです(申出手続が完了した際にも送信します。)。このため、代理人による申請の場合を含め、登記名義人となる者本人のみが利用しているメールアドレスを申請情報の内容とします。なお、登記名義人となる者のメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容としてください(オンライン申請の場合には「その他事項欄」に「権利者Aにつきメールアドレスなし」のように入力し、書面申請の場合には権利者のメールアドレス欄に「なし」と記載してください。その場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することを想定されています。)。
検索用情報の申出の方法
登記申請と同時にする検索用情報の申出は、検索用情報(前記の(1)から(5)までの事項)を申請情報の内容とする方法により行う必要があります。
オンライン申請をする場合には、前記(1)及び(3)の事項に加え、(2)、(4)及び(5)の事項の入力欄が設けられますので、所定の欄に各事項を入力します。
申請の種類ごとの様式・記載例については、法務局ホームページの「不動産登記の申請書様式について」に掲載されていますのでご覧ください。
申出手続が完了した旨の法務局からの連絡
登記申請及び申出に不備がなかった場合、申出のあった検索用情報や不動産の情報等を検索用情報管理ファイル(職権による住所等変更登記のために必要な事項を記録するファイル)に記録します。
この記録が完了したときは、申出のあったメールアドレスに宛てて、次に掲げる事項を記録した電子メールを送信されます。
(1) 申出手続が完了した旨
(2) 立件の年月日及び立件番号
(3) 不動産番号
(4) 認証キー(※)
(5) 申出を受けた登記所の表示
※ メールアドレス(登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先)を変更する際に必要となる10桁の番号、記号その他の符号です。
職権による住所等変更登記の対象となる不動産
登記申請と同時にする検索用情報の申出がされた場合の職権による住所等変更登記の対象となる不動産は、登記申請をした不動産に限られます。
令和7年4月21日時点で既に不動産の所有権の登記名義人である者については、別途、申出をすることによって、当該不動産を職権による住所等変更登記の対象とすることができます。
検索用情報の申出に関する添付情報
登記申請と同時にする検索用情報の申出をする場合には、登記申請において必要となる添付情報に加え、氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあってはローマ字氏名)及び生年月日を証する情報を提供することとされています(新規則第158条の39第2項)。
もっとも、登記申請においては、従来から、住民票の写し等の住所を証する情報を提供する必要がありますが、これによって上記情報を兼ねることができることなどから、追加で必要となる添付情報は基本的に生じません。