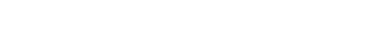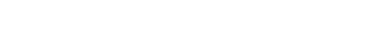司法書士が解説する相続登記義務化の実務
2025/10/09
相続登記の義務化が2024年4月に施行され、不動産の名義変更に関する制度が大きく変わりました。これにより、相続発生後一定期間内に登記手続を行うことが法律で義務付けられ、相続登記を怠った場合には過料の対象となる可能性があります。本ブログでは司法書士の立場から、相続登記義務化の背景や具体的な手続きの流れ、実務上の注意点について解説します。複雑な法制度のポイントを分かりやすく説明し、申請者がスムーズに対応できるようサポートする内容となっています。
これから相続登記を考えている方や手続を正しく理解したい方に役立つ情報となれば幸いです。ご一読ください。
目次
相続登記義務化とは?司法書士が語る制度の背景と目的
2024年4月から施行された相続登記義務化は、不動産の相続に関する登記手続を一定期間内に完了させることを法律で義務付ける制度です。これまで、相続登記の申請は任意とされていたため、名義変更が長期間行われず、所有者不明土地の増加が増える一因とも言われていました。義務化の目的は、こうした問題を解消し、土地の適正な管理や活用を促進することにあります。
したがって、相続が発生した場合には、落ち着いた後はできるだけ速やかに、戸籍収集や遺言書確認、遺産分割の協議を行うことになります。行動が遅れると当然登記申請も遅くなります。また、放置すれば、遺産の内容や相続人の把握など複雑なケースも増えるため、相続登記義務化の背景と目的を理解し、できるだけ速やかに正しい知識で確実に手続を行いましょう。
実務で知っておくべき相続登記の基本的な流れとは
相続登記の実務上の基本的な流れは、まず被相続人の死亡の後、遺言書の存否を確認し、遺言書がない場合は遺産分割の協議を行います。遺産分割の協議が整ったら遺産分割協議書を作成し、被相続人の生まれて亡くなるまでの戸籍、相続の権利ある人全員の戸籍、印鑑証明書などの必要書類を準備します。その後、遺言書又は遺産分割協議書に基づき登記申請書を作成し、管轄の法務局へ提出します。仮に、遺産分割の協議が整わない場合は、家庭裁判所に分割を請求することになります。
遺言書がある場合は遺言書の検認手続などが必要になりますし、遺産分割協議書も有効な記載が必要です。司法書士による専門的なサポートを活用しましょう。
義務化で変わる過料発生のポイントと頻出トラブルの回避法
相続登記の義務化により、不動産の所有権移転手続は従来にまして迅速かつ確実に行う必要があります。相続発生後、原則として3年以内に登記申請を行う義務が科され、「正当な理由」がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります(不動産登記法第164条第1項)ので注意が必要です。
「正当な理由」があると認められるケースとして、法務省は、次のような例示を示しています。
(1)相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2)相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3)相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4)相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5)相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
もっとも、これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事項に応じ、登記の申請をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められ、過料には当たらないとされています。
しかしながら、先にも述べましたが、放置すれば、遺産の内容や相続人の把握など複雑なケースも増えるため、相続登記義務化の背景と目的を理解し、できるだけ速やかに正しい知識で確実に手続を行いましょう。
具体的な手続の流れとしては、被相続人の戸籍謄本や遺言書又は遺産分割協議書など必要書類を準備し、司法書士への相談や代理申請を活用することが実務上推奨されます。頻出するトラブルとしては、相続人の間での遺産分割争い、書類不備による申請の遅延、また相続人の所在不明が挙げられます。
これらを避けるためには、早期の情報収集と正確な書類準備、そして専門家への相談が重要です。申請がスムーズに進むよう司法書士を活用しましょう。